
from 師範代Shinya
(→前回のつづき)
※英語学習のモチベーションを引き出すスキルを身につけるために、僕が最近学んだ「Co-Active コーチング」のセミナー体験談の続きです。
Co-Active コーチングを、英語学習コーチングと掛け合わせると、どんな効果が期待できるか?検証してみました。
通常の英語学習コーチングの場合は、
・生徒さんの英語学習目標をヒアリング
・その目標に沿った学習プランをアドバイス
・必要に応じて、レベルチェックテストを実施
・その他、Q&A
という流れです。
継続して定期的にコーチングする場合は、
・前回設定した学習プランを実行できているか?をチェック。
・進捗が遅い場合は、その理由を確認。場合によってはハッパをかける。
・必要に応じて、軌道修正。
という感じになります。
僕がこれまで提供してきた英語学習コーチングも、全体的な流れは上記のような感じです。
おそらくどのスクール英語コーチングを受けても、ざっくり全体的な流れは、上記と同じになるのではないかと思います。
これに、新しくCo-Active コーチングのスタイルを入れると、どうなるでしょうか?
ステップ①モチベーションの源を一緒に深掘りする
おそらく、ここが一番大きく変わる部分だと思います。
これまでは、英語学習の目標はあくまで「ヒヤリング」するものでした。
生徒さんの口から出た言葉をそのまま取り入れて、コーチングの中で目標に設定します。
でも、僕が今回、Co-Active コーチングを学んで気づいたことは、「人は、自分の本心にはなかなか気づけず、行動と価値観がズレていることが多い」ということです。
さらに、「自分のことは過小評価する傾向」があります。
一見、自信満々そうに見える人でも、心の底では自分を過小評価していることがあるのです。
たとえば、クライアントさんが、
「私がやりたいことは、これなんです。」
と言ったとします。
その後にコーチが、
「なぜ、それをやりたいと思うんですか?」
と質問します。
それを答えてもらっている間に、コーチは返事の内容だけではなく、クライアントさんの表情や声のトーンなどを注意深く観察します。
その情報を元に、次の質問をします。
たとえば、
「そのどんなところが、あなたにとって重要ですか?」
というような、オープンな質問です。
するとクライアントさんは、自分がこれまで自問自答すらしたことがないことを考え始めます。
出てきた答えを、コーチが丁寧に拾い、また次の質問を投げかける。
答えが出てこない場合は、焦らずゆっくり、思いつかない理由を一緒に探ってみる。
といったことを繰り返していきます。
すると最終的には、クライアントさん本人が自分で自分の本心や価値観に気づくのです。
それは、最初に言っていた目標と同じとは限りません。
むしろ、違うことの方が多いです。
コーチの役割は、あくまで「引き出すこと」で、「与えること」ではありません。
尋問とコーチングの違い
「コーチング中に、質問を投げかけられる」と聞くと、身構えてしまう人も多いです。
仕事の面接のように、尋問されているような気分になるのではないか?という恐れが出るのは当たり前だと思います。
でも、実際にコーチングを受けてみると、尋問されている感はまったくありません。
尋問のようなプレッシャーは、まったく感じないのです。
なぜでしょうか?
それは、「目的の違い」です。
仕事の面接の目的は、「面接を受けている人が、我が社の役に立つか?利益を生んでくれる人材になれるか?」という部分です。
つまり、面接官は「自分たちの利益のために質問している」とも言えます。
人手不足の会社の面接でも、余裕がある会社でも、その部分は変わりません。
そのため、質問は一方的になります。
「この仕事に応募した動機は、何ですか?」
と面接官が聞いた後には、面接官の頭の中では「アリか?ナシか?」のジャッジモードになっています。
聞き手がジャッジモードになっている時には、話し手にも必ず伝わります。
利害があると、人は心を開けない
「自分は今、目の前の相手にジャッジされている」と感じるのは、心理的に大きなプレッシャーになります。
ジャッジされているということは、「正解がある」ということです。
・この質問に対して、こう答えたら、採用される。
・逆にこう答えたら、落ちる。
というように、自分の答えの内容次第で、自分の評価が変わるというのは、心理的に「安心できる場」ではありません。
だから、人は尋問されたくないのです。
コーチングの目的
一方、コーチが質問する目的は、「クライアントが、より良い方向に行けるように手助けすること」です。
そして、コーチは話を聞いている間、「自分の考えやジャッジをすべて手放す」ことが求められます。
コーチがクライアントの答えをジャッジしていると、言葉に出さなくても、必ずクライアントに伝わります。
すると、クライアントはそれ以上話せなくなってしまいます。
クライアントが何を言ったとしても、コーチは心の中で「それは違うんじゃないか?」などとジャッジしない。それが大前提です。
そのために、コーチは自分の意見や価値観を手放すのです。
(僕が今回受けたセミナーでは、この「手放す練習」を、重点的に繰り返しやりました)
「ジャッジしない場作り」にフルコミットするからこそ、クライアントさんは安心して色々話せるのです。
もちろん、クライアントが「コーチの考えを聞きたい」と求めれば、コーチは自分の考えや体験を伝えます。
でも、それはあくまで、クライアントにとっての判断材料の一つとしての位置づけです。
どっちが正しいか?間違っているか?の勝負の世界ではないのです。
この、安心できる場作りができて初めて、クライアントは自分の本当の価値観に気づけるのです。
・・・つづく。

—————————————
※このブログに読者登録をしていただくと、最新の記事を1日1回、メールでお届けします。読者登録はこちらをクリックしてください。
↓↓↓

From 師範代Shinya(新村真也)
(やり直し英語達成道場 師範代)
※もくじは、こちら
自己紹介は、こちら





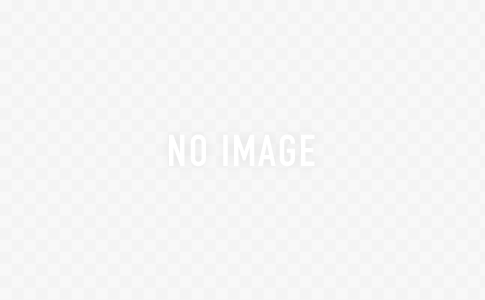






コメントを残す