
from 師範代Shinya
「英語を勉強しなきゃいけないのはわかっているけど、どうしても気が重い」
「教材を開くたびに義務感に押しつぶされる」
そんな気持ちを抱いたことはありませんか?
英語学習を長く続けるカギは「やらなきゃ」という外発的動機から、「やりたい」という内発的動機へシフトすることです。
今日は心理学の自己決定理論をベースに、「義務感ではなく楽しみとして英語を続ける方法」をお伝えします。
モチベーションには2種類ある
心理学では、動機づけには大きく分けて2種類があるとされています。
外発的動機づけ
外からの圧力や報酬によって動くこと。
・試験で点数を取るため
・ 昇進や転職の条件を満たすため
・周囲に評価されるため
このように「外部の評価」が基準になっています。
内発的動機づけ
自分の内側から生まれる興味や楽しさによって動くこと。
・好きな映画を字幕なしで観たい
・外国人と自然に会話を楽しみたい
・ 大好きな海外の本を英語の原書で読んでみたい
外からの評価ではなく「自分がやりたいからやる」状態です。
外発的動機のメリットとデメリット
外発的動機は、短期的にはとても強い力になります。
試験日が近づけば誰でも必死に勉強しますし、昇進がかかっていれば本気にならざるを得ません。
一方で、最大のデメリットは「状況が終わった途端に消える」こと。
試験が終わったら勉強がストップする、目標の資格を取った瞬間に教材を開かなくなる…
そんなケースは珍しくありません。
つまり、外発的動機は「スタートダッシュ」や「一時的な追い込み」には有効ですが、長期的な学習を支える力にはなりにくいのです。
内発的動機のメリットとデメリット
一方で、内発的動機には「やめたくてもやめられないほどの継続力」があります。
映画を観る、音楽を聴く、スポーツをするのと同じで、「やりたいからやる」状態に入ると、英語は義務ではなく楽しみになります。
ただし、ここにも落とし穴があります。
・見つけにくい:大人になってから「英語が楽しい!」と純粋に思えるきっかけを得るのは簡単ではありません。
・波がある:楽しさや興味は感情に左右されやすく、昨日は楽しかったけど今日は気分が乗らない、ということが起こります。
・長期目標とズレることも:楽しいから映画ばかり観ていても、TOEICの点数が上がらないというケースもあり得ます。
つまり、内発的動機は持続力に優れる反面、見つけるのが難しかったり、資格試験のような数値化できる成果につながりにくいこともあるのです。
自己決定理論が教える「続くモチベーション」
アメリカの心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンの提唱した「自己決定理論」では、人が内発的に行動を続けられる条件を3つ挙げています。
1. 自律性:「自分で選んでいる」という感覚があること
2. 有能感:「できるようになっている」と感じられること
3. 関係性:「人とつながっている」と感じられること
英語学習も、この3つを意識することで「やらなきゃ」から「やりたい」へと変えていけます。
「やらなきゃ英語」を「やりたい英語」に変える工夫
1. 好きな題材を使う
TOEICや英検の問題集ばかり解いていると、義務感が強まります。
日常会話、映画、音楽、旅行、スポーツなど、自分の興味あるテーマの英文を使って勉強すると、「もっと知りたい」という気持ちが自然に生まれます。
TOEICや英検などの本番試験を受け終わる前に、「終わったら次に何を使って勉強するか?」を決めておくと良いです。
2. 小さな成功体験を積む
「昨日より1文多く読めた」「オンライン英会話で一言通じた」など、些細でも達成感を意識しましょう。
また、今日勉強した範囲や、音読回数などを記録して、「自分の行動を目に見える状態にする」のもオススメです。
行動が積み重なっていく証拠を見ることで、有能感が高まり、やる気が内側から湧いてきます。
僕も、音読や瞬間英作文トレーニングの回数を毎回書いて見える化しています。
TOEICの点数がなかなか上がらずに焦っていた頃は、この見える化した数字を眺めることで、
「大丈夫!ちゃんと積み上がってる!」
という実感を持つことができました。
その経験を活かして、自分が今作っている英語レッスンのコースでも、受講生の方々には「毎日のトレーニングチェック表」をつけてもらっています。
3. 人との関わりを持つ
学習仲間や先生とのつながりはモチベーションを強力に支えます。
孤独に勉強していると「今日はやめようかな」となりやすいですが、仲間がいると「自分もやろう」と自然に思えるのです。
僕も以前は、同じ英会話スクールに通うクラスメイトと連絡先を交換し、英語学習仲間として一緒に集まって勉強していました。
今ではオンラインでカンタンに集まれるようになったので、自分のコースの受講生の方々が同じタイミングで一緒に勉強する「オンライン自習会」を開催しています。(お盆、年末、GWなどの長期休みに連日開催しています)
4. 数字以外のゴールを設定する
「TOEIC◯○点」だけでは義務感に縛られます。
「海外旅行で困らず現地の人たちとやりとりできる」「好きな本を原文で読む」など、自分にとってワクワクする目標を持つと、「やりたい気持ち」が強くなります。
外発と内発のハイブリッドで進める
では、外発的動機と内発的動機はどちらが正解なのか?
答えは「どちらもうまく活用すること」です。
・外発的動機は短期的な強制力。
・内発的動機は長期的な持続力。
両輪で使うことで、最強の学習サイクルができます。
外発で火をつけ、内発で燃やす
試験を申し込んで外発的にスタートし、教材は自分が興味ある分野にする。
「やらされ感」と「楽しさ」のバランスが取れます。
特に初心者のうちは、教材を試験内容とは違うものにしても大丈夫です。
TOEICはビジネス英語のイメージがあると思いますが、普段は日常会話のセリフを使って音読しても、ちゃんと点数にも反映されます。(ただし、700点以上を目指す場合には、ビジネス英単語の習得は必須になります)
内発で動機をつくり、外発で加速する
「字幕なしで映画を観たい」という内発的ゴールを持ち、進歩を数値化するためにTOEICを利用する。
達成感が可視化され、自信が積み重なります。
映画のセリフは早口で、いい加減な発音で話されることが多いので、慣れるとTOEICのリスニングがスローに聞こえるという現象が起こります。(ただし映画の種類によって、使われるボキャの種類が大きく変わるので、どのぐらいTOEICの点数に反映されるかの比率は変わります)
偏りを避ける
外発に偏ると → 試験後に燃え尽きる。
内発に偏ると → 楽しいけれど成長を感じにくい。
両方を組み合わせることで「続けられるし、伸びる」学習スタイルが完成します。
まとめ
英語を長く続けるには、「やらなきゃ」という外発的動機から「やりたい」という内発的動機へシフトすることが大切です。
・外発は短期の強制力、内発は長期の持続力。
・内発的動機は見つけにくいが、好きな題材・小さな成功・仲間との関わりで育てられる。
・外発と内発をハイブリッドで組み合わせると、自然に続き、成果も実感できる。
安心してください。
今は「やらなきゃ」と思っている人でも、必ず「やりたい」に変わる瞬間があります。
その火を絶やさないために、外からの期限と内からの楽しさ、その両方を味方につけて進んでいきましょう。
—————————————
※このブログに読者登録をしていただくと、最新の記事を1日1回、メールでお届けします。読者登録はこちらをクリックしてください。
↓↓↓

From 師範代Shinya(新村真也)
(やり直し英語達成道場 師範代)
※もくじは、こちら
自己紹介は、こちら









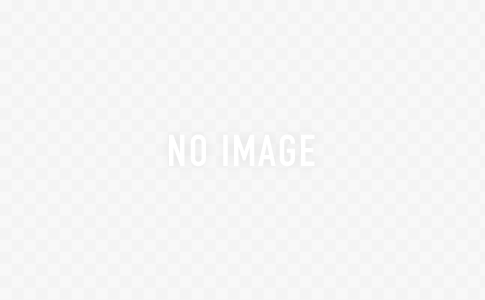



コメントを残す