
from 師範代Shinya
前回の記事では、僕がこの本を読んで衝撃を受けた内容のトップ3のうち1つ目、
①叱ることには依存性がある。人は誰かを叱っている時に、脳内に快感物質が出る。
をお伝えしました。
叱るという行為は、僕ら人間の本能に埋め込まれた強い欲求なので、誰でもハマる可能性があります。
そして、実は最も中毒性が高くなる時があるそうです。
それは、「叱る人自身の人生がうまくいっていない時」だそうです。
人間は他人を叱っている時には、自分の人生から目を背けることができます。
自分の問題と向き合うのがツラ過ぎる時に、他人の問題を解決することに意識を向けることで、一瞬でも苦しみから解放されるのです。
この「苦しみからの解放」というのが、快楽よりもより強い中毒性を持つと、この本には書いてありました。
確かに、奥さんと熟年離婚した男性が酒浸りになったり、家庭で愛を受けられなかった若者が薬物依存になったりするケースは多いです。
人は強いストレスを感じた時に、依存性の高いものを使って一瞬でも脳を解放しようとします。
その中の1つが、「叱る依存」というわけです。
たしかに、うっぷんを晴らすために部下を叱りつける上司というのは、よくドラマなどでも描かれることがあります。
朝、奥さんとケンカした男性が、出社してすぐに部下のアラ探しをして怒鳴りつける、みたいなシーンです。
(最近はパワハラ問題でそういうシーンはあまり描かれなくなりましたが、怒鳴らなくても叱ることはできます)
ネット上でキツいコメントを書く人達も依存症になっている
叱る対象は、目の前の人達だけではありません。
浮気をした有名人をネット上で叩く炎上行為も、実はこの人間の本能が暴走した状態だそうです。
他の人達が有名人を叱っているのを見ると、自分の「叱りたい本能」も刺激されて、似たようなキツいコメントを書き込んでしまうのです。
禁酒している人の目の前で、お酒を飲んでいる人達がたくさんいたら、誘惑に負けてしまうのと同じ感覚です。
週刊誌やテレビなどのメディアも、それが分かっているので、わざと視聴者の「叱る依存」を引き出すような見出しを付けて、有名人を悪者にします。
そうすることで、視聴率を稼げるからです。
このメカニズムが分かったことで、僕はアンチコメントを書く人達の心理がなんとなく理解できました。
アンチコメントは、言い換えると「他人を叱る言葉」です。
「あなたは間違っている。あなたは、こうすべきだ!」
といったコメントを書くことは、書いた人の中にある「叱る本能」を満たすことになります。
そうすることで、自分の人生から一瞬でも目をそむけることができ、苦痛から解放されるのです。
そしてポイントは、その人の元の性格に関係なく、すべての人間に「叱る本能」が備わっていて、きっかけさえあれば、いつでも暴走する可能性を秘めている、ということなのです。
叱る依存から脱却するには、「自分は今、叱る依存にハマっているかもしれない」と自覚することが第一ステップだと、著者の村中先生はおっしゃっています。
叱る依存になっていない時でも、「自分は大丈夫!」と思わずに、「いつでも依存症が発症する可能性がある」と思っておくことが、予防にもつながります。
②叱ることは、実は相手のためではなく自分のためにやっている。
叱ることが「叱っている人の本能を満たすための行為」だとすると、叱ることは実は自分のためにやっていることになります。
叱っている最中の人にこんなことを言ったら、
「そんなことはない!私はこの人のためを思って叱っているんだ!これは愛のムチだ!」
「この人は他人に迷惑をかけている。この人の行いを正すことは、社会のためになるんだ!私は正義を貫いているんだ!叱りたくて叱っているんじゃない!」
と反論されるケースが大半でしょう。
実は、これこそが、依存症に気づけない最大の原因だそうです。
叱っている人は、それが自分自身のためにやっているなんて、まったく感じていないからです。
むしろ、「君がちゃんとしないから、私は仕方なく叱ってやってるんだ!」ぐらいに思っているのが普通です。
この本によると、叱っている人はむしろ「自分が被害者だ」と思っているケースが多いそうです。
「この人が、私や周りの人達に迷惑を与えている。叱らないと、被害が拡大する。今のうちに止めないと!」
という思考回路です。
アンチコメントは「正義の剣」
ネットで、ひどい言葉遣いで有名人を叩いている人たちも、自分が「攻撃している」なんてまったく思っていないことが多いらしいです。
「浮気をしたこの俳優は、奥さんを傷つけた。私は、奥さんの代弁者だ!この俳優が調子に乗ってまた同じことをしないためにも、非難の声が必要なんだ!私はより良い社会を作るために、正義を実行しているのだ!」
と信じながら、必死にやっているのです。
そして、他のアンチコメントを見て、「ほら!他にも同志がたくさんいるじゃないか!これは正しいことなんだ!」と確信しながらコメントを書き続けるのです。
まさに、自分が正義の剣を振るって悪者を倒すヒーローになっているような感覚です。
浮気のように分かりやすいケースばかりではありません。
ちょっと調子に乗ってTVやネット上で失言をした人を、大勢で寄ってたかって叩く(叱る)シーンもよく見かけます。
人はそれぞれ「こうすべきだ」という自分の中にある常識や信念を持っています。
自分の常識と真逆の行動を取る人を見ると、本能的にイラッとして、叱りたくなってしまうのです。
でも、残念ながら叱るという行為は、「相手のためではない」ということです。
もし、相手のためであれば、叱ることには「効果がある」ことが前提になります。
効果とは、「叱られた人が新しい何かを学び、成長していくきっかけになる」必要があるのです。
それが、3つ目のポイント「叱ることには、ほとんど効果がないことが証明されている」につながっていきます。
・・・つづく。
p.s.11月にオンライン通学コースの体験セミンーを開催します。詳細はこちらの画像をクリックしてご確認ください↓↓↓
今回紹介した「叱る依存が止まらない」はこちら↓↓
—————————————
※このブログに読者登録をしていただくと、最新の記事を1日1回、メールでお届けします。読者登録はこちらをクリックしてください。
↓↓↓

From 師範代Shinya(新村真也)
(やり直し英語達成道場 師範代)
※もくじは、こちら
自己紹介は、こちら








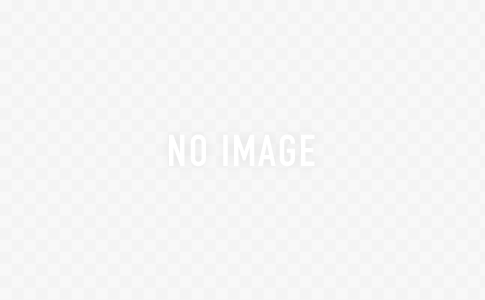






コメントを残す